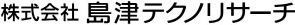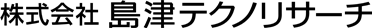法規制・規格


POPsなど有害物質の無害化支援
法規制・規格
残留性有機汚染物質(Persistent Organic Pollutants : POPs)は、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性を持ち、地球規模移動、拡散するため、一部の国々のみの取組では地球環境汚染の防止には不十分なことから、 国際的な取り組みとして2001年にストックホルム条約(POPs条約)が締結されました。
2004年5月に条約の批准国が50ヶ国を超え、発効されましたが、この条約ではPOPsとしてPCB・農薬類などを対象としています。
条約では、各国がとるべき対策として、
・製造・使用、輸出入の制限(附属書B)
・新規POPsの製造・使用予防のための措置
・非意図的生成物(附属書C)の排出の削減
・ストックパイルや、廃棄物の適正管理及び処理 等が定められています。
日本国内では、非意図的生成物(附属書C)の、ダイオキシン類・PCB・ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン・PCNについては、「ダイオキシン類対策特別措置法」 「PCB廃棄物の適正な処理に関する特別措置法」等により、排出削減計画が実行されるとともに、大気排出インベントリー作成が進んでいます。
当社は、国のPOPsモニタリング調査やインベントリー調査に参画しています。また、特にPCB等の無害化処理施設について、 処理に係る性能確認試験・周辺環境測定等を積極的に受託しております。処理過程における収支、入口検査、汚染の有無、安全性の確認、環境保全、PCB処理油の卒業判定、分解/除去の判定、周辺環境調査など、無害化処理ビジネスにも対応できます。
一方、トキサフェンとマイレックス(国内で使用履歴なし)以外の農薬は、平成13年調査で、全国24道県、168カ所の約4,400tが埋設されたままの状態でした。現在、埋設農薬を無害化する処理法が確立され、処理が進められています。
当社は、埋設農薬の処理に伴う調査も積極的に受託しています。
第3回締約国会議(COP3)までの対象12物質
| 農 薬 |
|
||||||||||||
| 工業製品 |
|
||||||||||||
| 非意図的生成物 |
|
※○は、重複して記載されているもの
当社は、POPs条約第3回締約国会議(COP3)以降にPOPs条約の附属書に追加された物質(New POPs等)や新たに対象物質とするよう提案されている物質について、GC-HRMSやLC-MS/MS等を用いた高感度、高精度の分析法を確立しています。
詳しくは、業務案内「POPs」をご覧ください。
関連情報
20190920