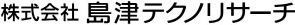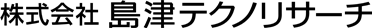第4回環境化学物質合同大会(第33回環境化学討論会)参加報告
第4回環境化学物質合同大会 参加報告
(第33回環境化学討論会/第29回日本環境毒性学会研究発表会)

「環境化学・毒性学におけるOne Healthアプローチ:人、動物、環境、社会が築く健康課題への解決策」
会 期:2024年7月15日(火)~7月18日(金)
会 場:「山形テルサ」および隣接の「やまぎん県民ホール」
主 催:(一社)日本環境化学会、日本環境毒性学会
大会長:渡部 徹(山形大学農学部)
実行委員長:第33回環境化学討論会 池中良徳(北海道大学)
第29回日本環境毒性学会研究発表会 加茂将史(産業技術総合研究所)
● 当社の研究成果発表内容 https://www.shimadzu-techno.co.jp/news/gakkai/news250613.html
● 環境化学物質合同大会の情報 https://j-ec.smartcore.jp/M022/forum/touron33
第4回環境化学物質合同大会において、当社は連名も含め、8題の研究成果を発表しました。
大会の概要や主な研究報告、講演の内容などをレポートします。
<大会の概要>

会場(山形テルサ)
第4回環境化学物質合同大会は、昨年度に引き続き環境化学物質に関わる2学会(第33回環境化学討論会、第29回日本環境毒性学会研究発表会)合同で開催されました。
総発表演題数は476題(特別講演2を除く)、口頭発表169題、ポスター発表263題、参加者数795名(展示スタッフを含めると900名超)となり昨年度よりも演題数が増え大変盛況な大会となりました。
一般の口頭発表やポスター発表でも8つの重点テーマセッションに加え、特別講演と8つの特別企画も別途設定され、会場のいたるところで活発な議論が展開されていました。
◇重点テーマセッション
- PFASの高精度分析技術における新たな展開
- PFASの環境・生体モニタリング
- マイクロプラスチックの動態
- マイクロプラスチックと関連化学物質の生物影響
- 農薬の環境動態・生物影響・リスク評価
- PPCPs・生理活性物質の動態・生物影響
- 高分解能質量分析計によるワイドターゲット・ノンターゲット分析の潮流
- 環境化学物質の学際的共同研究の成果と展望III
◇特別講演
講演者:「環境中の薬剤耐性菌とその発生源に関する研究」 西山正晃(山形大学・准教授)
「環境中に残留する抗菌薬と薬剤耐性菌との関わり」 花本征也(金沢大学・准教授)
◇特別企画
- 化学物質、廃棄物及び汚染に関する政府間科学・政策パネル(ISP-CWP)の設立と今後について(環境省主催)
- シグナル毒性と神経攪乱の評価に向けた革新技術(日本神経化学会共催)
- 室内環境における環境汚染問題を多角的に考える(室内環境学会共催)
- ハイブリッド環境質量分析(日本質量分析学会共催)
- 大気中揮発性有機化合物(VOC)の環境動態~VOC研究から大気環境問題を横断的に探る~(大気環境学会共催)
- 日韓共催シンポジウム: 韓国環境分析学会と日本環境化学会の連携強化のための共催シンポジウムJapan-Korea Joint Symposium: Joint Symposium to Strengthen Collaboration between the Korean Society for Environmental Analysis and the Japanese Society for Environmental Chemistry(韓国環境分析学会(The Korean Society for Environmental Analysis, KSEA)共催)
- 化学物質と共生する社会を目指して:健康と環境を衛る科学の役割(日本薬学会 環境・衛生部会共催)
- 環境化学物質のリスク学・環境毒性学とネイチャーポジティブ・TNFDとの節合点(日本リスク学会共催)
<主な発表内容>
本大会では、PFASをはじめ、プラスチック、農薬類、重金属、POPs類など、多岐にわたる分野で発表がありました。
中でもPFASは発表件数が大幅に増加し、全体の26%を占める主要なテーマとなりました。また、プラスチックについてもPFASに次いで発表件数が全体の14%と高く、PFASと合わせてそれぞれ2つの重点テーマセッションが組まれるなど、前回大会に引き続き高い注目度が伺えました。
テーマ別では、分析技術(網羅分析・機器分析)に関する発表が80件と最多でした。
特に網羅分析に関する発表が多く見られ、代替キャリアガスによるGC-MS分析や、ダイオキシン類分析の二重収束型質量分析計以外の装置での代替といった具体的な分析手法検討に関する報告も多数ありました。重点テーマセッションでもノンターゲット、ワイドターゲット分析に関するセッションが組まれており、未知環境物質の探索や効率的なスクリーニングが大きく関心を集めていることが感じられました。
自由集会では、6つのテーマについて活発な議論が交わされました。
特に、環境省 化学物質安全課主催の「第6次環境基本計画とは~新たな化学物質管理政策の展開」と経済産業省主催の「化審法における化学物質の安全性評価の現状と展望」においては、化学物質管理の情報共有体制などについて活発な意見交換が行われました。
今大会でも特別講演の「薬剤耐性問題に挑戦する環境研究」のほか、質量分析学会をはじめとした他学会との共催による特別企画など、幅広い分野での発表が見られ、専門分野の垣根を超えた学びや発見につながる貴重な機会となりました。
また、開催3日目に行われた懇親会では参加者同士の交流や意見交換が行われ、会の最中には山形大学の花笠サークルによる演舞が披露され、活気あふれるパフォーマンスに会場は盛り上がりました。

(懇親会の様子 (協力:山形大学花笠サークル四面楚歌))
来年は、長崎市で6月23日から26日に第5回環境化学物質合同大会(第34回環境化学討論会/第30回日本環境毒性学会研究発表会)としての開催が決まりました。
当社はこの討論会に毎年、複数題の研究発表を行っています。実行委員として運営側にも関わっています。今後も本学会への参加を通じて、環境化学物質研究のさらなる活性化を目指して、分析機関の一員として、研究・分析技術支援を継続し、社会貢献していきたいと考えています。