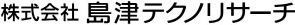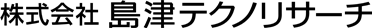概要


POPsなど有機ハロゲン化合物の分析
概要
環境中での残留性が高いPCB、DDT等のPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分なことから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」により国際的に協調して廃絶、削減に向けた取り組みが行われています
当社は、POPs条約の対象物質や、新たに対象物質とするよう提案されている物質について、GC-HRMSやLC-MS/MSを用いた高感度、高精度の分析法を確立しています。環境省の「POPs残留状況の監視事業(大気、生物)(通称POPsモニタリング調査)」等のPOPsの大規模調査を2002年度から受託し、また、グリーン調達支援として、電機電子機器や自動車関連、玩具等の材料や製品の品質管理サポートを実施するなど、豊富な実績があります。
環境や生体中のモニタリング、材料や製品中の含有量調査、POPs廃棄物処理施設の各種実証試験などを分析で支援します。
■POPsについて
POPsは毒性が強く、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性があり、人の健康又は環境への悪影響を有する化学物質のことで、以下のような性質を持っています。
| ● | 有害性 |
| 発ガン性や神経障害、免疫毒性、ホルモン異常など。特に「環境ホルモン」として疑われている物質が多くあります。 | |
| ● | 生物蓄積性(低水溶性・高脂溶性で生物濃縮しやすい) |
| 脂肪に溶けやすいため、生物の脂肪組織に濃縮されやすい性質を持っています。そのため、より高次の捕食者の体内に高い濃度で蓄積する傾向があります。 | |
| ● | 難分解性(環境中への残留性が高い) |
| 化学的安定性を求めて作り出されたため、環境中に放出されても分解されにくく、長く環境中に残留します。 | |
| ● | 長距離移動性(バッタ効果:Grasshopper Effectで温暖な地域から中緯度や極地へと移動する) |
| POPsは環境中で分解されにくいため、発生・使用時に飛散したり、揮発したりして、空気中に拡散したものが、大気の流れに乗って移動し、冷たい空気に触れることで地上に降下します。化学物質がバッタが飛び跳ねるように長距離を移動することから「バッタ効果」と呼ばれています。 |
分析・試験項目
当初のPOPs条約の対象物質は以下の12物質です。
| 物質名 | 附属書 | 用途 |
|---|---|---|
| アルドリン | A | ● |
| ディルドリン | A | ● |
| エンドリン | A | ● |
| DDT | B | ● |
| ヘプタクロル | A | ● |
| クロルデン | A | ● |
| ヘキサクロロベンゼン(HCB) | A and C | ●▲ |
| マイレックス | A | ● |
| トキサフェン | A | ● |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | A and C | ▲■ |
| ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD) | C | ■ |
| ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF) | C | ■ |
なお、POPs条約では、2年に1回の締約国会議において、対象物質が順次追加されています。COP4以降に追加された物質を一般にNew POPsと呼びます。以下に追加された対象物質のリストを示します。
| 会議 | 開催年月 | 追加数 | 物質名 | 附属書 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| COP4 | 2009.5 | 9 | α-ヘキサクロロシクロヘキサン(α-HCH) | A | ● |
| β-ヘキサクロロシクロヘキサン(β-HCH) | A | ● | |||
| γ-ヘキサクロロシクロヘキサン(γ-HCH、リンデン) | A | ● | |||
| クロルデコン | A | ● | |||
| ヘキサブロモビフェニル(HBB) | A | ▲ | |||
| ヘキサブロモジフェニルエーテル(ヘキサBDE) ヘプタブロモジフェニルエーテル(ヘプタBDE) |
A | ▲ | |||
| テトラブロモジフェニルエーテル(テトラBDE) ペンタブロモジフェニルエーテル(ペンタBDE) |
A | ▲ | |||
| ペンタクロロベンゼン(PeCB) | A and C | ●▲■ | |||
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)又はその塩及びPFOSF | B | ▲ | |||
| COP5 | 2011.5 | 1 | エンドスルファン | A | ● |
| COP6 | 2013.5 | 1 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) | A | ▲ |
| COP7 | 2015.5 | 3 | ヘキサクロロブタジエン(HCBD) | A and C | ▲■ |
| ペンタクロロフェノール(PCP)とその塩及びエステル類 | A | ● | |||
| ポリ塩化ナフタレン(PCN) | A and C | ▲■ | |||
| COP8 | 2017.5 | 2 | デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE) | A | ▲ |
| 短鎖塩素化パラフィン(SCCP) | A | ▲ | |||
| COP9 | 2019.5 | 2 | ジコホル | A | ● |
| ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩及び PFOA関連物質 |
A | ▲ | |||
| COP10 | 2022.6 | 1 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質 | A | ▲ |
| COP11 | 2023.5 | 3 | デクロランプラス | A | ▲ |
| UV-328 | A | ▲ | |||
| メトキシクロル | A | ● | |||
| COP12 | 2025.5 | 3 | クロルピリホス | A | ● |
| 中鎖塩素化パラフィン | A | ▲ | |||
| 長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質 | A | ▲ |
※各物質が最初に附属書に追加された会議の欄に物質名を示しています。
なお、新規提案物質として、ポリ臭素化ジベンゾ-p-ジオキシン及びジベンゾフランについて、更なる情報収集を行い、検討を進めることがPOPRC21において決定されました。
法規制・規格
■日本国内での対応について
POPs条約の対象物質については、製造・使用・輸出入を原則禁止(附属書A)、特定の目的・用途での製造・使用に制限(附属書B)、非意図的な生成をできる限り廃絶することを目標として削減(附属書C)などの対応が求められます。
日本国内においては、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法※)」や「農薬取締法」などにより対象物質の製造・使用・輸出入の規制が行われています。また、ごみ焼却などに伴って発生するダイオキシン類などの非意図的生成物については、排出規制を行うとともに、各発生源別の排出量の目録(排出インベントリー)が整備されています。
※化審法の第一種特定化学物質
化審法の第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質として、政令により定められた物質です。製造又は輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入制限や第一種取扱事業者に対する基準適合義務及び表示義務等が規定されています。
第一種特定化学物質についてはこちらから >> (経済産業省HP)
■海外での規制について
POPs規則(Regulation (EU) 2019/1021)は、EU域内における残留性有機汚染物質(POPs)の管理を目的とした包括的な法規制です。
この規則は、POPs条約の規定をEU法として取り入れ、以下の事項を通じてPOPsの製造、使用、輸出入を厳しく管理しています。
附属書Ⅱ: 制限付きで製造、上市および使用が許可される物質
附属書Ⅲ: 非意図的に生成されるPOPs
附属書Ⅳ: POPsを含む廃棄物に関する基準値
附属書Ⅴ: 廃棄物の処理に関する規定
2024年6月~9月にUV-328、デクロランプラス、メトキシクロルが新たに附属書Iに追加(あるいは追加する改正案が公表)されました。EU加盟国では、これらの物質が制限濃度を超える濃度で含まれる製品の製造、使用、上市が原則として禁止されます。
分析・試験方法
■環境省による調査と分析動向
当社は、環境省の「POPs残留状況の監視事業(大気、生物)(通称POPsモニタリング調査)」等の大規模調査を、調査開始当初より継続して受託しています。
以下にその分析動向について示します。
| ・ | 日本では環境省を中心に「黒本調査」(エコ調査と改名)として、従来はGC-LRMSレベルで継続的な調査を実施 |
| ・ | 2002年度より世界に先駆けてGC-HRMSを用いてPOPsモニタリングが始動 |
| ・ | 2003年度よりPOPsモニタリングにトキサフェン、マイレックス、trans-ヘプタクロルエポキサイドが追加 |
| ・ | 2008年度よりPOPsモニタリングにポリブロモジフェニルエーテル類(PBDE)が追加 |
| ・ | 2010年度よりPOPsモニタリングにペンタクロロベンゼン、ヘキサブロモビフェニル、クロルデコン、PFOS、PFOAが追加 |
| ・ | 2011年度よりPOPsモニタリングにエンドスルファンが追加 |
| ・ | 2012年度よりPOPsモニタリングにヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)が追加 |
| ・ | 2016年度よりPOPsモニタリングにペンタクロロフェノール、短鎖塩素化パラフィン、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン(大気)が追加 |
| ・ | 2018年度よりPOPsモニタリングにジコホル(生物)が追加 |
| ・ | 2019年度よりPOPsモニタリングにジコホル(大気)が追加 |
| ・ | 2020年度よりPOPsモニタリングにPFHxSが追加 |
当社は、世界に先駆けて、大気・生物試料中のこれらNew POPsの分析法を確立し、この大規模調査に貢献しています。
■POPsの分析方法
当社は、POPs条約対象物質及び新規提案物の測定分析について豊富な実績があります。これ以外の物質についてもお気軽にお問い合わせください。
| 化学物質名 | 分析方法 |
|---|---|
| ダイオキシン類(PCDD、PCDF) | GC-HRMS(EI)法 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | GC-HRMS(EI)法 |
| アルドリン | GC-HRMS(EI)法 |
| ディルドリン | GC-HRMS(EI)法 |
| エンドリン | GC-HRMS(EI)法 |
| DDT | GC-HRMS(EI)法 |
| ヘプタクロル | GC-HRMS(EI)法 |
| クロルデン | GC-HRMS(EI)法 |
| ヘキサクロロベンゼン(HCB) | GC-HRMS(EI)法 |
| マイレックス | GC-HRMS(EI)法 |
| トキサフェン | GC-Orbitrap/MS(NCI)法 |
| HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)類 | GC-HRMS(EI)法 |
| クロルデコン | LC-MS/MS(ESI(negative))法 |
| ポリブロモジフェニルエーテル類(PBDE) デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE) |
GC-HRMS(EI)法 |
| ヘキサブロモビフェニル | GC-HRMS(EI)法 |
| ペンタクロロベンゼン | GC-HRMS(EI)法 |
| PFOS又はその塩 | LC-MS/MS(ESI(negative))法 |
| PFOA又はその塩 | LC-MS/MS(ESI(negative))法 |
| PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質 | LC-MS/MS(ESI(negative))法 |
| エンドスルファン類 | GC-HRMS(EI)法 |
| ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD) | LC-MS/MS(ESI(negative))法 |
| ヘキサクロロブタジエン(HCBD) | GC-MS(EI)法、GC-HRMS(EI)法 |
| ペンタクロロフェノール(PCP)とその塩及びエステル類 | (誘導体化)GC-HRMS(EI)法 |
| ポリ塩化ナフタレン(PCN) | GC-HRMS(EI)法 |
| 短鎖塩素化パラフィン(SCCP) | GC-Orbitrap/MS (NCI、EI)法 |
| ジコホル | GC-HRMS(EI)法 |
| デクロランプラス | GC-HRMS(EI)法 |
ダイオキシンの分析については、「ダイオキシン類」
PCBの分析については、「PCB」
ヘキサブロモビフェニル(HxBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)、デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)、
ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)の分析については、「臭素系難燃剤」「PBB/PBDE」
PFOS又はその塩、PFOA又はその塩、PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質の分析については、「PFOS/PFOA/PFHxS」
ポリ塩素化ナフタレン(PCN)の分析については、「PCN」
短鎖塩素化パラフィン(SCCP)の分析については、「SCCP」のページもご参照ください。
関連情報
参考文献
環境省の化学物質分析法開発調査において、NewPOPs等の物質の分析法を確立しています。
当社が確立した方法(参考文献)を以下に示します。(リンク先:国立研究開発法人国立環境研究所HP)
20210115